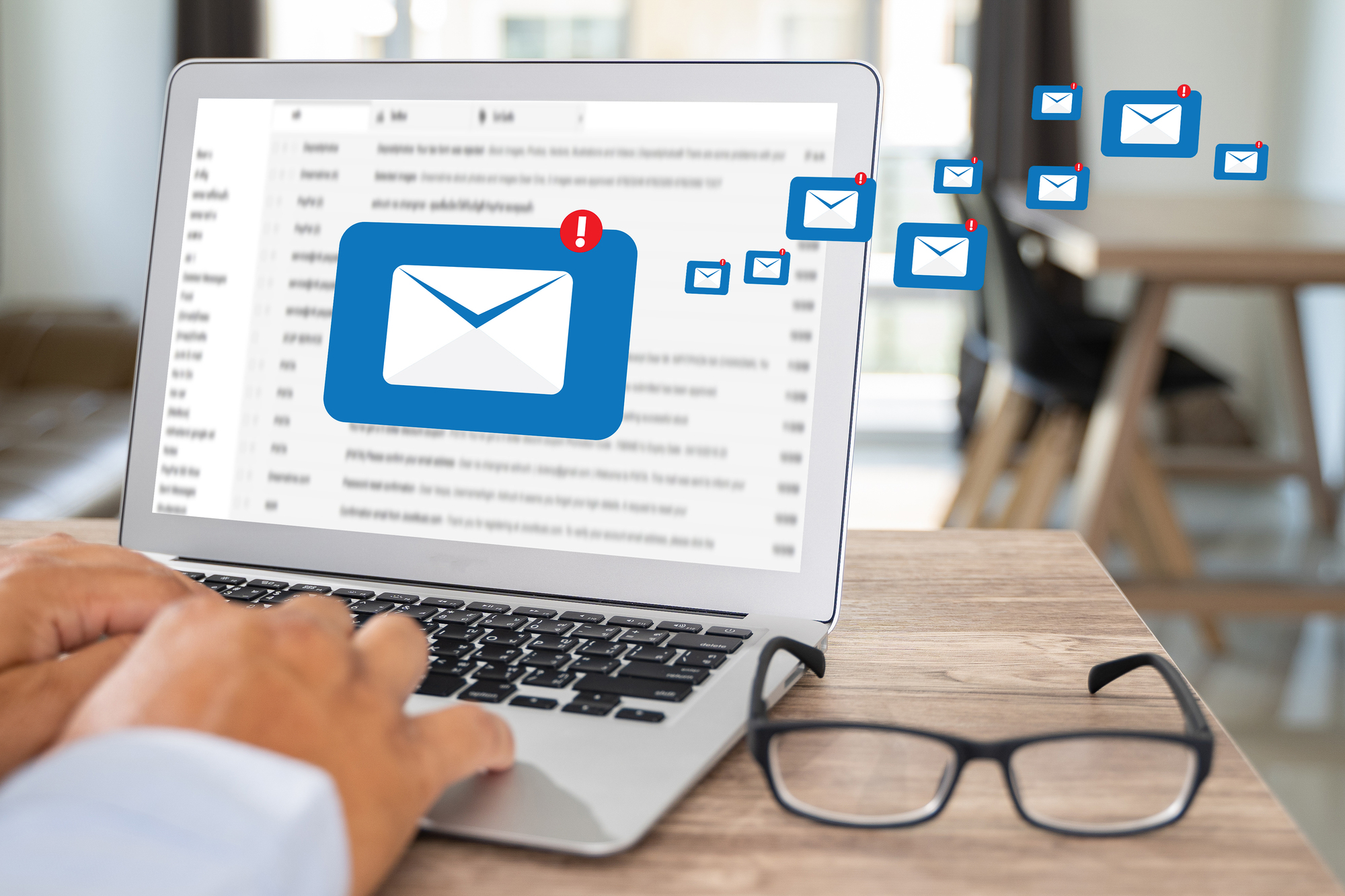会社の避難訓練は必要?事前準備やシナリオ作りの手順・ポイントを解説

豪雨や地震、台風など、日本各地では毎年のように天災が発生しています。そのため、いつ発生するかわからない大きな災害や事件・事故のために日頃から備えておく必要があります。
国の防災基本計画においては「企業防災の推進を位置づけている」と内閣府が公表しています。企業としては、従業員の命を守り事業を継続させるため、いつどのような災害に遭っても対応できるよう、対応を進めなければなりません。
企業防災にはさまざまな準備がありますが、そのなかでも避難訓練は従業員を守るために必須です。ただ避難の経路を確認するだけではなく、避難訓練の効果を高めるには「シナリオ」作りが必要不可欠です。どのような災害で、どんな状況に陥っているのかを細かく決めることで、より有事の際に役立つ訓練になります。
この記事では避難訓練の重要性や事前準備、シナリオ作りの手順・ポイントを解説します。
目次
01会社での避難訓練はなぜ重要? 02避難訓練における事前準備とは? 03避難訓練におけるシナリオ作成手順 04シナリオ作りのポイント 05情報共有ツール、安否確認ツールの事前準備 06企業の情報共有ツール、安否確認ツールなら「オクレンジャー」がおすすめ 07会社での避難訓練は必ず年に一度行いましょう01会社での避難訓練はなぜ重要?
天災・人災にかかわらず、災害は企業の事業継続を困難にする大きなリスクです。2011年の東日本大震災ではその後10年間で、震災による直接的・間接的な被害によって2,000件以上もの企業が倒産しています。
もし災害により大きな被害を受ければ、流通や製造といった企業活動がストップするだけではなく、従業員の危険にさらされる可能性もあります。被害を最小限に防いで従業員と事業を守るためには、企業における災害への対策は非常に重要といえます。
そのなかでも避難訓練は、非常時の行動を従業員に周知する貴重な機会です。実際、東日本大震災では「釜石の奇跡」と言われる小中学校の事例があります。日頃の防災意識の高さと避難訓練のおかげで、多くの生徒の命が救われました。避難訓練は非常時に従業員の安全を確保するため、企業活動を継続するためにも欠かせません。
避難訓練は会社の義務

企業の避難訓練は、消防法で年1回以上実施することが義務づけられています。特定用途防火対象物・非特定用途防火対象物によって回数が異なり、それぞれ以下のように分類されます。
特定用途防火対象物:百貨店、ホテル、映画館、病院、飲食店など
非特定用途防火対象物:学校、工場、図書館、博物館、倉庫など
特定用途防火対象物は百貨店やホテルなど、不特定多数の人が集まる場所です。災害のタイミングによって被災する人が異なるため、年2回以上の避難訓練が義務づけられています。同時に、特定の人が利用する一方で避難が困難な場合も特定用途防火対象物に該当します。具体的には福祉施設や幼稚園といった施設が当てはまります。
特定用途防火対象物で訓練を行う際は、事前に管轄する消防署に通報しなければなりません。消防法施行規則第3条第11項で定められているので、避難訓練実施前に消火・避難訓練通知書を消防署に提出しましょう。必要に応じて消火器を借りたり、訓練指導をお願いしたりもできますので、事前に相談しておくとよいでしょう。
一方、非特定用途防火対象物は学校や工場といった施設が当てはまります。火災の起こる確率の低さや避難のしやすさを考慮し、年1回以上の避難訓練が義務づけられています。
02避難訓練における事前準備とは?

会社で避難訓練を行うには、以下の5つの事前準備が大切です。
避難経路の確認
まずは避難訓練を行う前に自社の避難経路を確認しておきましょう。避難時に使う階段や通路、非常口、非常ハッチなど、どのようなルートを通るのか、実際に通れるのかをチェックします。
実際に災害が発生した場合は、倒壊や火災などで本来のルートが塞がれてしまう場合も考えられます。複数の避難経路があるか確認しておくとよいでしょう。
避難訓練のシナリオを用意
避難訓練において最も重要とも言えるのが、シナリオの設定です。
完成度が高い訓練シナリオを用意できれば、訓練にリアリティが生まれます。リアリティのある避難訓練によって災害を疑似体験することで、ただマニュアルを読むよりも従業員全員の理解・防災意識が深まり、もしもの時に冷静に対処しやすくなります。同時に、リアルな訓練を経験することで、BCPや防災マニュアルの内容が実際の災害に対して有効かどうかを検証できます。
もし、マニュアル通りに行かなかったり想定外の事が起こったりした場合はマニュアルの内容に不足があるかもしれません。そのときは、どの部分に問題があるのかを確認し、更新しましょう。限られた時間を有効活用するためにも、避難訓練におけるシナリオは大変重要です。
役割分担と担当者の任命
避難訓練を行う際は、あらかじめ担当者を任命して役割分担することが重要です。
以下に、避難訓練を行う際に設定される主な担当の例を挙げ、それぞれの役割を説明します。
- 全体統括(訓練責任者)
- 概要:訓練全体の企画・運営・進行を担当し、現場でのリーダーシップを担います。
- エリア責任者
- 概要:各エリア(部署やフロアなど)の避難統括を担当します。責任者は、そのエリアでの安全な避難を監督します。/li>
- 避難誘導員
- 概要:避難経路の案内や誘導を担当します。主に、安全確保と混乱防止を目的とします。
- 要配慮者支援担当
- 概要:高齢者、妊娠中の女性、身体障害者など、特別な配慮が必要な人々の避難をサポートします。
- 安否確認担当
- 概要: 訓練中や訓練終了後に、参加者の安否を確認し、関係各所に報告します。
- 緊急対応班
- 概要:緊急事態発生時の初動対応を担当します。
- 記録・評価担当
- 概要: 訓練の様子を記録し、結果を評価する役割を担います。
- 広報・連絡担当
- 概要:訓練情報の事前周知や、訓練中の連絡・報告を行う役割です。
- 監査・評価担当(第三者監視役)
- 概要:訓練が計画通りに実施され、課題点が浮き彫りになるよう監視・評価を行います。
- 後方支援担当
- 概要:避難訓練に必要な物資や設備を準備する裏方の役割です。
- 特殊任務担当(場合による)
- 火災訓練の場合の消火班
- 地震訓練の場合の通報班
- その他、状況に応じて設定される役割(例: 実際の避難場所を確保する担当)。
上記すべてを任命する必要はありませんが、会社の規模や事業内容によって、必要となる役割分担を決めましょう。そして、避難訓練で与えられた任務を実践してもらうことが重要です。
情報共有ツール、安否確認ツールの整備
避難訓練に取り入れてほしいのが、現場の情報共有をリアルタイムで行うこと、そして社員の安否確認です。いずれにおいても無事に避難し、安全を確認したのちに行っていただくアクションとなりますが、会社の事業継続として非常に重要なフローとなります。
災害時でも安定して情報共有のできるシステムや、社員のスマートフォンから安否を回答してもらい、会社側で安否情報を一括管理できるなど、緊急時や災害時に特化した機能を持つ専用システムを備えておくのが良いでしょう。

実施時間を消防署へ通知
避難訓練を行う際は実施時期と時間、訓練内容を管轄の消防署へあらかじめ通知しましょう。
避難訓練の通知書は、それぞれの自治体がフォーマットやガイドラインなどをWEBで公表しています。作成した書類はFAXやメール、郵送などで消防署に送ります。
また、避難訓練時に非常ベルを鳴らしたり館内放送を流したりといった近隣への影響が出る場合は、近隣のビルや住人へ事前に周知しておきましょう。本当に火災・事故が起こったと誤解されない配慮が大切です。
03避難訓練におけるシナリオ作成手順
避難訓練のシナリオが重要なことは前述しましたが、実際にどのように作成すればよいか迷われる方も多いでしょう。ここでは避難訓練のシナリオ作成手順をステップごとに解説します。
目標を明確にする
まずは避難訓練を通して何を達成・確認したいのかを、明確に設定しましょう。
具体的には「BCPを理解してもらう」「防災マニュアルが機能しているか検証する」「負傷者が出た時の対応」などが挙げられます。目標が明確であれば、従業員の意識を高められ、より実際の災害に対応しやすくなるでしょう。
災害状況を設定する
次に、どのような災害において避難を必要とする状況に陥っているのかを具体的に設定しましょう。
災害の種類・発生の日時・場所・規模などを、具体的に設定すればするほど避難訓練のリアリティは高まります。例えば火災を想定した避難訓練の場合、以下のような設定が考えられます。
災害発生場所…どの建物・フロアで火災が発生したのか
災害発生時間…いつ火災が発生したのか
災害規模…火災の規模はどれくらいで、何人が被災する・しているのか
災害期間…鎮火にどれだけ時間を要するのか
外部への影響…社外への延焼はあるのか
細かく設定されていればいるほど、より被災状況をイメージしやすくなります。
被災時は時間経過により状況が変わるので、時間経過を盛り込むとよりリアルな訓練になります。こうした災害状況を設定する際は、過去に起きた災害や事故などを参考にすると決めやすくなります。
また、火災のような一般的に行われる避難訓練だけではなく、会社によってはサイバー攻撃やパンデミックなどの被害を想定しての訓練が必要な場合もあります。会社の事業や状況に応じて、リスクが高く発生する恐れがある災害への対策を行うことが大切です。
状況・被害別の対応方法を決める
設定した状況・被害に対して、どのような対応をとるべきか決めましょう。具体的には、災害が発生して、終息するまで時系列順に考えます。
同時に、会社内で役割分担を決めるとよいでしょう。決められた人に役割が偏らないよう、従業員全員にそれぞれに役割を割り振ることで当事者意識を高められます。指揮係や救護班、消火班、避難誘導班といった災害時に必要と想定される役割を考え、それぞれにリーダーを設定します。リーダーが不在になることも考慮し、サブリーダーのようなポジションも決めておくとよいでしょう。
04シナリオ作りのポイント
避難訓練のシナリオを最大限生かすための大切なポイントを紹介します。
定期的にシナリオを見直す
どれだけクオリティの高いシナリオを作っても、何度も使い回していると形式的な訓練になってしまいがちです。ただシナリオをなぞるだけの訓練では恒例行事となってしまい、形だけの意味がない訓練になってしまいます。これではシナリオで設定した目標を達成できません。
避難訓練のマンネリ化を防ぐ対策として、以下のような対策を紹介します。定期的にシナリオを見直して、形骸化を防ぎましょう。
訓練の度にシナリオを変更する
基本的な対策として、シナリオを使い回さないという方法があります。
複数のシナリオを用意し、想定される状況を火災から台風に変更したり、目標設定を変更したりすることでさまざまな状況下に備えられます。また、前回行った避難訓練の反省事項に基づいて再度シナリオを組み立てるのもおすすめです。
訓練内容を非公開にする
事前に参加者に避難訓練の内容やシナリオを伝えず、非公開のまま行うという方法も効果があるでしょう。
いつも決まった内容の訓練では、緊張感・当事者意識のない避難訓練になってしまいます。シナリオの一部もしくは大部分を伏せて実行すれば、何が起こるかわからず従業員の緊張感は高まるでしょう。実際に災害が起こった時にはいつどのような被害を受けるかわかりません。より実際の状況に合わせるためには効果的だといえます。
防災関連施設を活用する
日本各地にある防災関連施設を活用して、避難訓練を行うという方法もあります。
例えば大阪市立阿倍野防災センターでは、地震発生から火災発生、消火、救出、応急救護まで一連の流れを体験できます。実際に地震や火災などの体験ができる防災施設を、法人で研修利用してみるのもおすすめです。
防災マニュアルやBCPに沿って作成する
避難訓練のシナリオは、防災マニュアルやBCPに沿って作成しましょう。
会社における避難訓練は、従業員の身の安全を守ることだけが目的ではありません。作成した防災マニュアルやBCPが実際に使えるかどうかを確認するのも重要な目的です。
防災マニュアルやBCPに矛盾が生じれば、社内が混乱し、避難や復旧が遅れる可能性があります。本末転倒にならないためにも、事前の訓練によって実際に活用できるかを確認するとよいでしょう。
また防災マニュアルやBCPは従業員全員が理解し、実践できなければ意味がありません。避難訓練を通してマニュアルに対する理解や習熟度を上げ、いざという時に冷静に落ち着いた行動がとれるようにしましょう。
05情報共有ツール、安否確認ツールの事前準備
これらを避難訓練に取り入れる際の注意点として以下の事前準備をしておきましょう。
システムの導入と目的の明確化
目的の共有: 安否確認システムを導入する意図(例: 災害時の社員の安否確認、迅速な情報共有)の明確化が必要です。
方法の選定: 導入するシステムが、自社の規模やニーズに適しているか確認します。例えば、メール、電話、専用アプリなど。
従業員への周知と教育
使い方の説明: システムの操作方法を全従業員に周知し、使い方に関する簡易マニュアルを配布します。
定期的なトレーニング: 実際に使う場面を想定した訓練を実施し、従業員が緊急時にもスムーズに利用できるようにする。
従業員の連絡先情報を安全に扱う
データの機密保持: 個人情報を安全に管理し、不正アクセスや漏洩対策を徹底する。
システムの動作確認・テスト運用
動作テスト: 実際の緊急時に問題なく機能するかを事前に確認します。通信状態やレスポンス速度をテストする。
06企業の情報共有ツール、安否確認ツールなら「オクレンジャー」がおすすめ
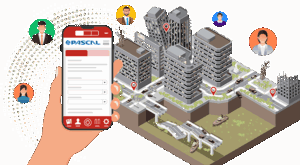
おすすめのツールはパスカルの「オクレンジャー」です。
導入企業・団体は4,000以上、ユーザー数は累計220万人の実績があります。
日本初の特許を取得した緊急連絡網・安否確認システムのスマホアプリです。
特長
フルクラウド型なので、インターネットの繋がる端末であればいつでもどこでもログイン可能です。
緊急連絡はもちろん、社員の安否確認や社員同士で情報共有できる災害掲示板を備えています。
天災時には気象庁の情報と連携して情報を自動で受け取ることができ、あらかじめ条件やテンプレートを設定しておけば、自動で一斉配信も可能です。
シンプルかつ直感的なデザインで、誰でも簡単に操作可能です。
無料トライアル
緊急連絡ツールの導入を検討中の企業担当者は、ぜひ無料トライアルに申し込んでください。
無料トライアルはこちら:https://www.ocrenger.jp/trial/
資料請求・お問い合わせ
機能やコストの確認など、トライアル前に資料請求を希望される方は、お問い合わせからご連絡ください。
お問い合わせはこちらhttps://www.ocrenger.jp/inquiry/
07会社での避難訓練は必ず年に一度行いましょう
会社においての避難訓練は従業員の命を守るだけではなく、有事の際に企業活動が滞りなく行えるようにするための意味もあります。社内全体の意識を高めるためにも、必ず年1回以上は実施しましょう。
同時に、リアリティのあるシナリオを活用することで、実際に被災したときの迅速な行動につながります。人命を守り、事業をいち早く復旧させられるようなシナリオを作り、従業員に浸透させましょう。
そして、社員の安否確認や正確かつリアルタイムな情報伝達の実現を目指すことで、BCP対策の強化も図っていきましょう。
監修者情報:株式会社パスカル
オクレンジャー ヘルプデスク
オクレンジャーヘルプデスクは、年間6000件以上のお客様の声と向き合い、課題を解決してきたオクレンジャーを知り尽くす専門部隊です。
業界随一のサポート体制を目指し、日々お客様の声や社会情勢、最新の防災情報等を勉強し情報収集することで、お役に立てるよう邁進しています。