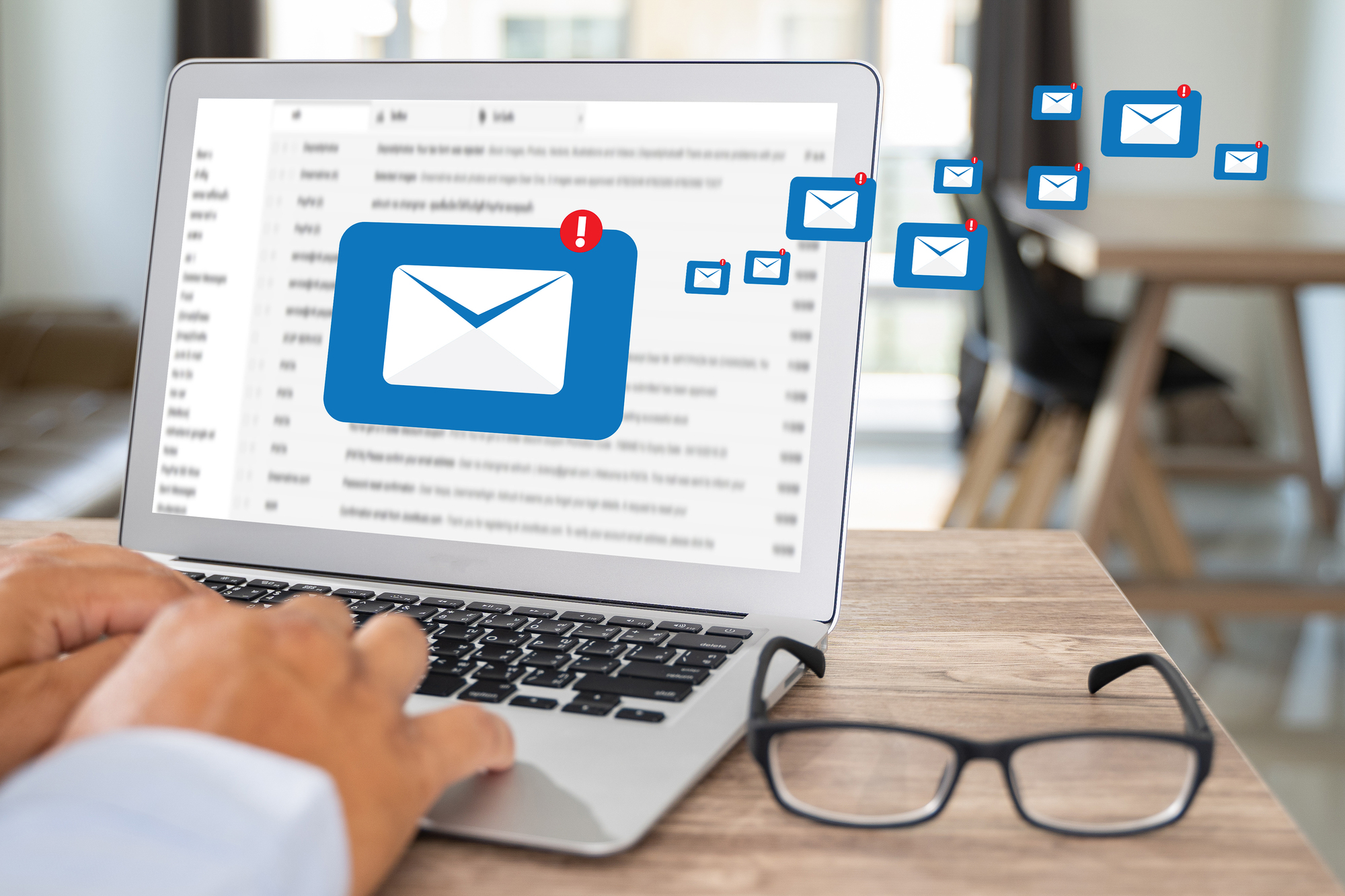企業の緊急連絡網の作り方とは?連絡手段の方法も確認

地震大国の日本では、緊急時の連絡体制を構築しておくことが重要です。そして、災害やトラブルが発生した際、効率的に従業員へ連絡する方法として挙げられるのが緊急連絡網です。緊急連絡網作成のポイントを押さえ、万が一の事態に備えておくとよいでしょう。この記事では、企業向け緊急連絡網の作成のコツや緊急連絡の手段、緊急連絡網を活用するポイントなどについて紹介します。
01企業向け緊急連絡網とは?
そもそも緊急連絡網とは、災害やパンデミックが発生した際に迅速な連絡を行なうために、誰から誰へ、どのような順番で連絡するのかを決めておくものです。学校では緊急連絡網の作成が義務付けられているため、なじみがある人も多いのではないでしょうか。非常時に備えて、企業においても緊急連絡網を作成しておく必要があります。危機管理マニュアルまでは整備できない場合も、緊急連絡網だけは用意しておくのが賢明です。
企業において想定しうるトラブルは枚挙にいとまがありません。地震や台風などの自然災害はいうまでもなく、自社工場での火災、個人情報の流出、オフィスビルのシステム障害など、あらゆるトラブルが考えられます。企業向け緊急連絡網では、これらのトラブルすべてに対処できるような体制を構築しなくてはなりません。また、連絡が流れていくフロー図や連絡手段についても全社員で共有する必要があります。二次災害を防ぐうえで、緊急連絡網の作成は重要なポイントだといえるでしょう。
02企業向け緊急連絡網の作成のコツ
企業向け緊急連絡網を作成するときは、押さえておくべきポイントをまず理解することが大切です。ここからは、記載項目や発動条件、ルール作りなど、企業向け緊急連絡網の作成のコツについて解説します。

記載項目の確認
まずは企業向け緊急連絡網に記載する項目を確認しておきましょう。主な記載項目は、従業員の連絡先と連絡する順番の2つです。連絡先については、電話番号だけでなくメールアドレスも記載するようにしておけば、メッセージを残して伝えやすくなるでしょう。電話番号は主に携帯の番号を記載する場合が多いと考えられますが、従業員が固定電話を持っている場合はそちらも併記しておくとよいでしょう。また、緊急連絡網を社内共有する際には、オフィスの電話番号を欄外に載せておけば、従業員が忘れてしまった場合も安心です。
メールは連絡のスピードで電話に劣りますが、災害時は電話がつながらなくなる場合もあります。トラブルの詳しい内容を伝えたり、多くの人に一度に連絡を取ったりする場合にはメールが便利です。ほかにも、連絡手段としてSNSやチャットツールを利用するのも一つの方法です。電話やメールで連絡がつかないときの保険として考えておくとよいでしょう。
混乱を防いでスムーズに情報を伝達するために、連絡する順番を決めておくことも重要です。通常の業務で下から上への連絡フローが決まっているように、上から下へ情報が伝わる緊急時の連絡フローも用意しておきましょう。ただし、フローを重んじるあまり連絡が遅れては意味がないため、柔軟な対応が必要です。
緊急連絡網を活用する前に、取りまとめ役についても確認しておく必要があります。緊急連絡網を使うのは、一方通行で情報を伝達するときだけではありません。例えば、従業員の安否を確認したい場合、グループ単位で回答をまとめて上に報告することになります。誰が取りまとめ役を担うのか、最終的な報告は誰に行うのかといったことも事前に決めておきましょう。安否の連絡はメールで報告するなど、連絡手段もあらかじめ決めておくとスムーズに情報が集まります。
発動条件はどうするか
企業向け緊急連絡網を使うと全従業員に連絡がいくため、やみくもに発動させるわけにはいきません。適切なタイミングで活用するためにも、緊急連絡網の発動条件をあらかじめ決めておきましょう。一般的に、緊急連絡網の発動条件には内的なものと外的なものの2パターンがあります。内的な発動条件とは、責任者が緊急事態であると判断したときに緊急連絡網が使われることです。自然災害の場合は一刻も早く連絡を回す必要があるため、責任者がいない場合の対処法も考えておく必要があります。
一方、外的な発動条件を採用する場合、気象庁や政府の発表を緊急連絡網発動の指標とすると良いでしょう。例えば、大雨・洪水特別警報の発令、震度5以上の観測などが挙げられます。客観的な情報を引き金に設定するため、判断に迷う心配がありません。ただし、うまく機能させるためには従業員全体が外的な発動条件を認知している必要があります。発動条件について明確なルールを定め、会社全体で共有しておきましょう。
想定通りに行かなかったときのルール作り
緊急連絡網が必ずしもスムーズに機能するとは限りません。前述のとおり、責任者の不在によって適切なタイミングでの発動ができない場合もあるでしょう。また、課長がいないときにその部下全体に連絡がいかなくなるような事態も想定されます。連絡がつかないときは次の人に連絡する、連絡がつかなかったことについて取りまとめ役の人に報告するなど、想定通りにことが運ばなかったときのルールも作っておきましょう。
このとき、大切なのは「1時間以内に」「30分おきに」といったように、具体的な数字をルールに含めることです。連絡がつかなかった人に対しては30分おきに連絡を入れるなど、明確なルールを設けることで人は行動を起こしやすくなります。発動条件が外的なものである場合も、発令から30分以内に連絡がこなければ次の人に連絡するといったルールを決めておけば、緊急連絡網をうまく活用できるようになるはずです。
03緊急連絡をするときの連絡手段とは?

緊急連絡をするときの連絡手段にはいくつかの種類があります。それぞれのメリット・デメリットを押さえ、適切な方法を取り入れるとよいでしょう。ここからは、緊急連絡をするときの連絡手段について紹介します。
緊急連絡網を全社員に渡す
まず挙げられる方法が緊急連絡網の活用です。前段落で紹介したポイントに気を付けながら緊急連絡網を作成し、電話で連絡が取れるように全社員に渡しておきます。電話さえあれば連絡が取れ、新たなシステムを導入するコストがかからない点が緊急連絡網のメリットだといえるでしょう。
一方で、緊急連絡網はデメリットもあります。まず、全員に情報を伝達するまでに時間がかかる点です。いくらグループ分けされてても、一人ひとり順番に連絡を取り合う必要があるため、社員数が多いほど全員に連絡が行き届くまでの時間がかかります。また、もし連絡網が途中で滞った場合、状況が分からなくなる可能性もあるため、徹底してルールを周知する必要があります。
また、緊急連絡網には個人情報流出の恐れもあります。全社員に携帯電話の支給をしていない場合、会社所有の電話ではなく、個人の電話番号を載せる必要があります。社内のだれでも確認できる書面に記載するにあたり、必ず本人の許可を取らなくてはなりません。また、紙で保存してうっかり落とした場合、全社員の連絡先が流出する可能性もあります。全員がすぐに確認できるだけではなく、セキュリティ対策も万全にする必要があります。
安否確認システムを利用する
近年注目を集めている安否確認システムを利用するのも効果的な方法です。安否確認システムは緊急連絡に特化したサービスで、緊急連絡のメッセージを全従業員に向けて一斉に送信することができます。また、災害状況に応じて指示の内容を細かく編集することも可能です。メッセージを開封したかどうかも責任者側で確かめられ、従業員も自身の安否を簡単に報告できます。最近ではスマートフォンを持っている人が多いため、アプリで安否確認ができるサービスの提供もあります。緊急連絡網と異なり、個人情報をまとめて保管する必要もなくなります。従来の緊急連絡網のデメリットを避け、スピーディーな緊急連絡を実現したいのであれば、安否確認システムの導入が賢明だといえるでしょう。
なお、安否確認システムを導入する際はコストがかかるので注意が必要です。導入コストに見合うだけの価値があるかどうかをよく検討したうえで、使用するシステムを選ぶとよいでしょう。また、システムの管理体制によっては肝心な時にサーバーがダウンして利用できなくなる可能性があるため、サーバーをどのように管理しているのかといった点についても調べておく必要があります。
LINE・SNSを活用
LINEやチャットなどのSNSを活用して緊急連絡を取る企業も増えてきています。SNSで緊急連絡を行なうメリットは、格式張らず、気軽に情報のやり取りができることです。部署などのチーム単位でグループを作り、グループ内で一斉に安否確認ができるため、効率的な手段だといえます。
一方で、デメリットとして挙げられるのは、社用のスマートフォンが支給されていない場合は個人のアカウントでグループに加入しなくてはならないことです。仕事とプライベートを分けたいと考える人も多く、反対意見が出る可能性もあるでしょう。また、SNSによる緊急連絡には情報漏えいのリスクがつきまといます。そのため、個人利用専用のSNSではなく、ビジネスに特化したSNSを使用するのが賢明です。
メールの配信サービスを使う
メールの配信サービスとは、特定のアドレスにメールを送ることで、あらかじめリストアップしておいたアドレスへ向けて一斉にメールが送られるサービスのことです。トラブルが発生した際、迅速に全従業員へ情報が伝達できるため、スピードという点では効果的だといえます。また、メールなので電話よりも詳しい情報を伝えることが可能です。
しかし、メールでは受け取った側が読んだかどうかを確かめることができません。回答の収集にも手間がかかるため、結果的に責任者の業務負担が増える恐れもあります。メールの配信サービスを導入する際は、回答の集め方などを事前に考えておく必要があるでしょう。
04緊急連絡網を活用する際のポイント
緊急連絡網を十分に活用するためには、そのデメリットを理解し、ポイントを押さえた運用を心がける必要があります。まず、緊急時には通信回線が混雑するため、スムーズに連絡が取れない可能性があるでしょう。実際に、東日本大震災の際には平常時の50~60倍の通話が集中し、電話がつながりにくくなったといわれています。こうした回線の混雑に備えて、電話以外の連絡手段を確保しておくことが大切です。
また、選ぶ連絡手段によっては社員の個人情報を預かることになります。雑な管理は情報流出につながり、会社の信用を落とす事態にも陥りかねません。緊急連絡網に関わる個人情報は、セキュリティ面に配慮しながら管理する必要があります。
05非常時の連絡手段を事前に用意しましょう
緊急連絡網を作成しておけば、トラブルが発生したときも迅速に従業員へ情報を伝達できるようになります。連絡先や連絡する順番、発動条件、運用ルールなどを準備し、いざというときに役立つ連絡網を構築しておきましょう。ただし、緊急連絡網では従業員の個人情報を適切に管理する必要があります。また、回線の混雑によって電話がつながらない場合もあるでしょう。これらのデメリットをカバーする方法として、安否確認システムの導入をおすすめします。
緊急連絡網・安否確認システム「オクレンジャー」は、従業員の安否をアプリやメールで素早く簡単に確認できるサービスです。国内外にサーバーを複数設置しており、国内で大規模災害が発生しても安定的にシステムを利用できます。セキュリティ対策は万全で、責任者による個人情報の管理も一切不要です。確実かつスピーディーに安否確認がしたいのであれば、「オクレンジャー」をぜひご利用ください。
監修者情報:株式会社パスカル
オクレンジャー ヘルプデスク
オクレンジャーヘルプデスクは、年間6000件以上のお客様の声と向き合い、課題を解決してきたオクレンジャーを知り尽くす専門部隊です。
業界随一のサポート体制を目指し、日々お客様の声や社会情勢、最新の防災情報等を勉強し情報収集することで、お役に立てるよう邁進しています。