 お役立ちトピックス
お役立ちトピックス

避難生活での健康被害

避難生活と聞くと「地震」のイメージが強いですが、
「台風」「大雨」「火山の噴火」等でも避難生活をしなくてはならない場合があります。
今回はそんな避難生活で注意しなければならない健康被害についてご紹介します。
避難生活で起こりやすい健康被害には以下のようなものがあげられます。
ここではそれぞれどのような症状が起こるのか、
また発症しないようどのような対策をすれば良いのかをご紹介いたします。
01生活不活発病
症状
特に高齢者に起こりやすい症状で、体を動かす機会が減ることで
筋力が低下する、関節が固くなるなどして徐々に動けなくなることがあります。
対策
身の回りのことができる方には、なるべく自分で行ってもらう、役割を与える、
可能な作業に参加してもらえるよう呼びかけましょう。
可能であれば杖等の福祉用具を準備することも予防につながります。

02エコノミークラス症候群(肺塞栓症
症状
食事や水分を十分に取らない状態で、車などの狭い座席に長時間座り足を動かさないと
血行不良が起こり、血液が固まりやすくなります。
その結果血の固まりが足から肺などへ飛び、
血管を詰まらせ肺塞栓などを誘発する恐れがあります。
対策
定期的に体を動かし、十分に水分をとるようにしましょう。
できるだけゆったりとした服を着るようにし、
胸の痛みや片足の痛み・赤くなる・むくみなどがある場合は
早めに救護所や医療機関に相談しましょう。

03インフルエンザ、肺炎などの感染症
症状
下痢等の消化器系感染症や、風邪・インフルエンザ等の呼吸器系感染症です。
対策
こまめに手洗い、うがいをしましょう。可能であればマスクを着用しましょう。
水が出ない場合は、擦り込み式のエタノール剤やウェットティッシュがあると良いでしょう。
下痢の症状がある場合、脱水にならないようこまめに水分補給をしましょう。
また、下痢や嘔吐物の処理は直接手を触れないように適切に行うことが大切です。

04破傷風
症状
口が開かない、首筋が突っ張る、飲食物を飲み込みにくいなどの症状があります。
やがて全身けいれん、後弓反張などが起こり、呼吸困難を伴う場合もあります。
対策
がれきの撤去の際には長袖・長ズボン・手袋の上に厚手のゴム手袋をする、
厚底の靴を履くなどしてけがを防ぎましょう。
また、けがをした場合には、そこから破傷風に感染する可能性があります。
土などで汚れた傷は放置せず、手当てを受けるようにしましょう。
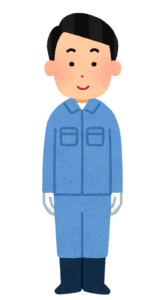
05低体温症
症状
手足が冷たくなって震えてきます。
つじつまが合わないことを言う、ふらつく、震えていた人が温まらないまま震えがなくなる、
意識がもうろうとするなどの症状もあります。
特に高齢者や子どもがなりやすいです。
対策
地面に敷物をしく、風を除ける、濡れたものは脱いで、毛布にくるまる等の対応をしましょう。
顔・首・頭からの熱は逃げやすいので、帽子やマフラーで保温しましょう。
体温を上げるために栄養、水分の補給も大事です。
-300x300.png)
-300x300.png)
06こころの健康被害
症状
・イライラする、怒りっぽくなる
・眠れない
・動悸、息切れで苦しいと感じる
など、心配や不安から現れる症状です。
対策
まずは休息や睡眠をできるだけとるようにしましょう。
不安・心配の多くは時間の経過とともに回復することが知られています。
これらを和らげる呼吸法として
「6秒で大きく吐き、6秒で軽く吸うを朝夕5分ずつ」行う方法もあります。
自分の中に気持ちや思いをため込まず、吐露することが重要です。
保健師や専門の相談員がいる場合はそちらに相談するのも良いでしょう。

避難生活では「トイレ」や「水・食料」「お風呂」などに困るという声が多いので、
健康被害に関して考えることが少ないかもしれませんが、上記の症状はどなたでも起こる可能性があります。
特に小さなお子さんや高齢者のご家族がいる方は注意が必要です。
※本記事は、下記ホームページの情報を基に株式会社パスカルが作成しました。
・厚生労働省「避難所生活を過ごされる方々の健康管理に関するガイドライン」
監修者情報:株式会社パスカル
オクレンジャー ヘルプデスク
オクレンジャーヘルプデスクは、年間6000件以上のお客様の声と向き合い、課題を解決してきたオクレンジャーを知り尽くす専門部隊です。
業界随一のサポート体制を目指し、日々お客様の声や社会情勢、最新の防災情報等を勉強し情報収集することで、お役に立てるよう邁進しています。





