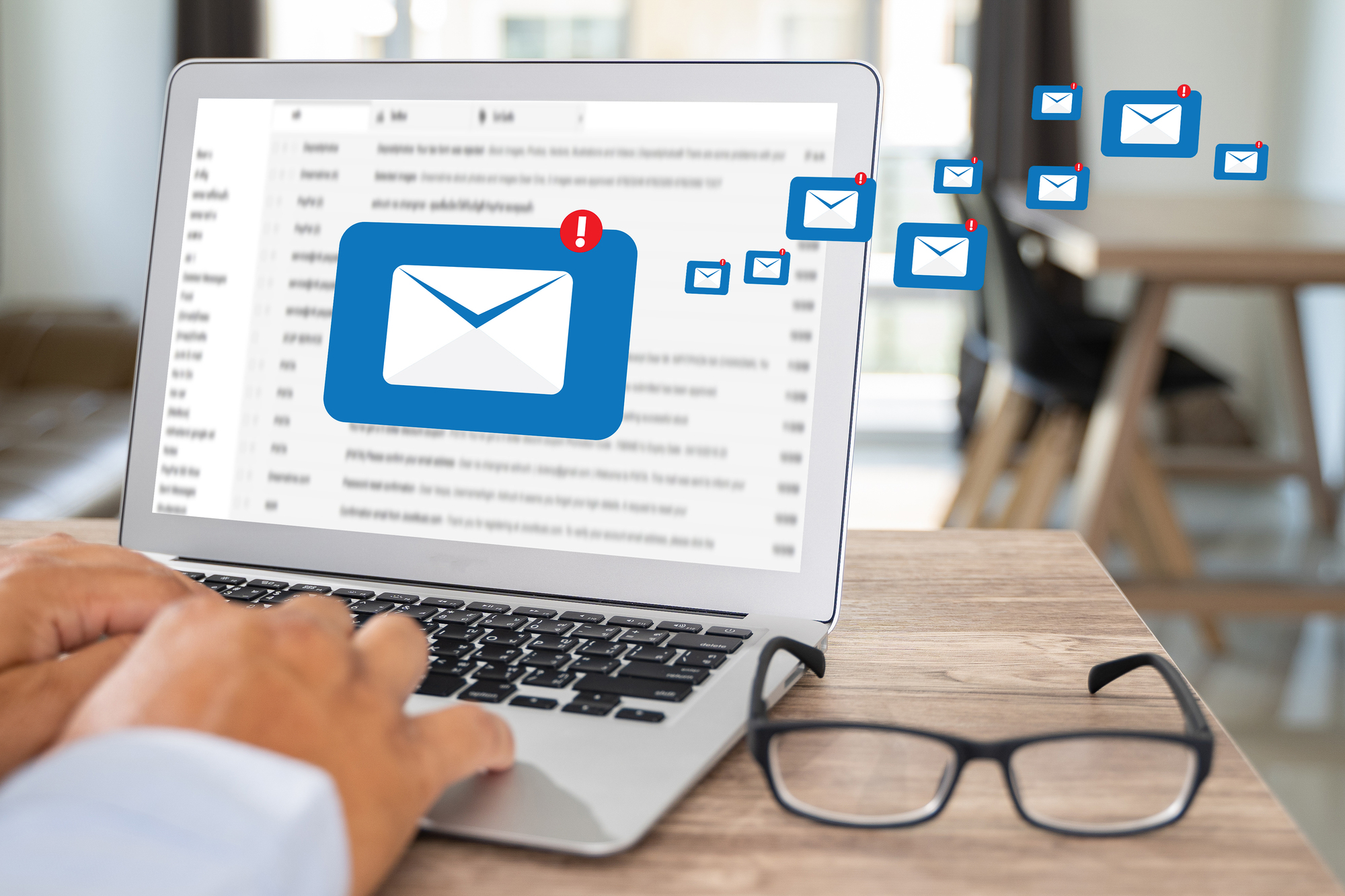リスクマップとは?活用方法などについて解説

日本は昔から自然災害がとても多く、近年では東日本大震災による地震や津波、西日本を中心とした平成30年7月豪雨による土砂災害などが挙げられます。災害による被害を最小限に抑えるために使用するものが「リスクマップ」です。リスクマップは土砂災害や洪水、津波などによって生じる被害を地図上に示したもので、災害時の避難経路を把握し、事前に対策を講じる際に役立ちます。
私たちは災害に備えてリスクマップをどのように活用すれば良いのでしょうか。今回はリスクマップでわかる情報、活用方法などをご紹介します。
01リスクマップとは

リスクマップとは、災害による被害予想図・想定図、被害予想区域や避難場所、避難経路などを表した地図で、自然災害による被害の軽減や防災を目的としています。
リスクマップを作成するためには、その地域の土地の成り立ちや災害の要因となる地形・地盤の特徴、過去の災害履歴などの情報が必要です。防災地理情報は国土地理院によって提供されており、国や地域の行政機関が作成・発行していることが一般的です。
リスクマップを利用することで、災害発生時であっても二次災害の発生箇所を予測しながら安全に避難することができます。
国土交通省の調査によると、2014年8月20日に広島市で発生した豪雨による犠牲者の発生場所と、リスクマップの危険箇所を照合したところ、犠牲者の76%が危険エリア内で亡くなっていたことがわかりました。(※)
「リスクマップに表示されていることがすべて本当に起こる」というわけではありませんが、リスクマップの情報は過去実際に起こった災害の情報を元に導き出された予測データです。お住まいの地域ではどのようなリスクが生じるのか、リスクマップを通して事前に確認しておきましょう。
※出典:洪水・土砂災害のハザードマップの意義と注意点 | 国土交通省(2021年11月10日)
02リスクマップでわかる情報
リスクマップでわかる情報は、主に「土砂災害」「道路災害情報」「洪水・津波浸水域」の3つです。それぞれの内容について詳しく見ていきましょう。
土砂災害
土砂災害のリスクマップは、土石流や急傾斜地の崩壊、地すべりや雪崩といった被害を想定して作成されており、災害リスクが高いエリアを「赤」、中程度のエリアを「オレンジ」として表示していることが一般的です。
「自宅の周りに土砂災害のリスクが高い箇所はあるか」といったことを確認し、日頃から災害発生に備えて準備をしておきましょう。
道路災害情報
道路災害情報のリスクマップは、土砂崩れや落石といった自然災害が起きた際に通行規制が敷かれる可能性がある区間や、洪水・津波によって通行が困難なおそれのある区間を表示しています。道路災害情報を事前に確認しておくことで、災害発生時に近隣の避難所まで安全な経路で向かうことが可能です。
洪水・津波浸水域
洪水・津波浸水域のリスクマップは、災害発生時に予想される浸水深を色分けして表しています。浸水深の色分けに共通表記はなく、自治体によってさまざまです。
近年ゲリラ豪雨による水害が頻発しており、河川の増水や堤防の決壊によって海から離れた地域であっても甚大な被害が発生することが増えています。日頃からリスクマップを活用して水害リスクを認識し、災害発生時の危険箇所や避難場所について正しい情報を知っておきましょう。
03リスクマップはどこでもらえる?
冒頭でご紹介したように、リスクマップは国土地理院が提供している防災地理情報を元に国や各自治体が作成しています。
リスクマップを手に入れる方法は「市区町村役場の窓口」と「リスクマップポータルサイト」の2つが一般的です。それぞれについて詳しくご紹介します。
市区町村役場の窓口
リスクマップは近隣の市区町村役場の窓口で入手することができます。公民館や自治センターなどにも置いてあることがあるため、「リスクマップを入手したいけど、どこに行けば良いかわからない」という方は市区町村役場に問い合わせてみるのがおすすめです。
リスクマップポータルサイト
リスクマップポータルサイトとは、国土地理院によって運営されているサイトで、居住地区だけではなく全国のリスクマップを見ることができます。「土砂災害」「道路災害情報」「洪水・津波浸水域」それぞれのデータを一つの地図上で重ねて見れる機能も。インターネット上でいつでも最新情報を手軽にチェックできるメリットもあります。(※)
※出典:防災・災害対応 | 国土交通省 国土地理院(2021年11月10日)
04リスクマップの活用方法

リスクマップはただ見るだけではなく、安全なルートを経由して自宅から地域の避難所へ実際に足を運んでみることが大切です。ここからは、リスクマップの活用方法についてご紹介します。
周辺の「指定緊急避難場所」を把握する
長く同じ地域に生活していても「地域の避難所がどこに該当するのかわからない」という方もいらっしゃるのではないでしょうか。リスクマップを確認することで、地域の指定緊急避難場所が一目瞭然です。災害が起こる前に指定避難所の場所を理解しておくことで、有事の際であっても冷静に避難ができるでしょう。
緊急時の通行規制ルートを把握する
国道や県道などの大通りは「特定緊急輸送道路」などに指定されていることが一般的です。一般車両の通行が制限されるため、「自宅近くの道路は緊急時に通行規制となるのか」「緊急時にどのようにして避難所に行くか」といったことをリスクマップから読み取っておくのがおすすめです。
災害リスクを理解して有事に備える
リスクマップから地域の災害リスクについて理解することで、さまざまな面で有事に備えることができます。災害時に家族で集合する場所を決めたり、自宅周辺の被害予測情報を元に備蓄用の食料を用意したりすると良いでしょう。
05定期的にリスクマップを活用して災害に備えよう
リスクマップの概要や活用方法などについてご紹介しました。自然災害の事前防災を目指し、情報面で支援するのがリスクマップです。日本は昔から災害大国でしたが、東日本大震災を踏まえて太平洋沿岸地域の津波浸水想定の見直しが行われるなど、防災意識が高まっています。
お住まいの地域のリスクマップで被害予想を確認し、災害時に備えて日頃から対策をしましょう。
監修者情報:株式会社パスカル
オクレンジャー ヘルプデスク
オクレンジャーヘルプデスクは、年間6000件以上のお客様の声と向き合い、課題を解決してきたオクレンジャーを知り尽くす専門部隊です。
業界随一のサポート体制を目指し、日々お客様の声や社会情勢、最新の防災情報等を勉強し情報収集することで、お役に立てるよう邁進しています。