 お役立ちトピックス
お役立ちトピックス

企業ができる水害対策には何がある?

近年大型台風のみならず、局地的な豪雨の発生頻度が高くなっている日本。元々、海や川の水位より低い土地で生活をしている場所も多く、堤防の決壊や土砂災害により大きな被害が生じることは少なくありません。
水害はどこであっても発生するリスクがあります。そのため、企業は緊急時であっても継続して事業を行えるように、あらかじめ水害対策を講じておく必要があるでしょう。
企業ができる水害対策にはどのようなことがあるのでしょうか。今回は企業における水害対策の必要性や具体的な水害対策などについてご紹介します。
01企業における水害対策の必要性

水害とは、大雨や台風などの多量の降雨によって引き起こされるもののほか、高潮や津波による災害の総称です。
世界各国の年間降水量は880mmであるのに対して、日本の年間降水量は1,788mmと約2倍に相当します。(※) 豪雨に加えて日本は地震大国であるため、津波や高潮といった海の災害にも注意する必要があるのです。
企業が受ける水害の例として、製造工場やオフィスの浸水が挙げられます。これらが浸水すると機械が稼働しなくなったり、従業員の命が危険に晒されたりするリスクが生じます。いずれも企業活動において欠かせない貴重な財産であるため、企業は水害のリスクに備えてあらかじめ対策を講じる必要があるのです。
企業ができる水害対策については、後ほど詳しくご紹介します。
※出典:水害・土砂災害の発生要因と社会構造の変化 | 国土交通省(2021年11月12日)
02水害の種類
水害の種類として「洪水」「氾濫」「高潮」「津波」の4つが挙げられます。それぞれについて正しく理解し、適切な方法で対策するようにしましょう。
洪水
洪水は大雨によって河川を流れる水量が急激に増えることです。河川の水量が増加することで、堤防の浸食や決壊、橋の流出などが起こることもあります。日本の河川は長さが短く、勾配が急であるため、雨がやんでも1~2日程度は急な河川の増水に注意しましょう。
氾濫
氾濫は洪水によって河川から水が溢れ出ることで、「外水氾濫」「内水氾濫」の2つに分けられます。
氾濫が起こりやすい地域の特徴は、標高が低いということです。谷のようにくぼんでいる地形や、川辺よりも低い土地などは河川が氾濫しやすい傾向があります。それぞれの特徴について詳しくご紹介します。
外水氾濫
外水氾濫とは、多量の雨によって河川が氾濫したり、堤防が決壊したりすることで市街地に水が流れ込むことです。外水氾濫は勢いよく水が流れ込むため、河川に近いエリアほど被害が大きくなる傾向があります。
規模が大きい河川で外水氾濫が起きると、住宅や自動車を押し流すほどの水が市街地に溢れ出てくることがあるため、逃げ遅れてしまう人が出る可能性もあります。外水氾濫は土砂を含んだ水が流れ込むため、内水氾濫よりも復旧まで時間がかかってしまいます。
内水氾濫
内水氾濫とは、都市の排水能力を超える多量の雨が降り、排水が雨量に追いつかずに氾濫することです。
内水氾濫はさらに細かく分けることができ、通常の内水氾濫のほか、河川の水が排水路を逆流して起こる「湛水型内水氾濫」があります。外水氾濫は広範囲に被害が広がるリスクがあるのに対して、内水氾濫の被害は限定的といった特徴もあります。
内水氾濫は標高の低い土地で起こりやすく、谷地やゼロメートル地帯、干拓地などは発生リスクが高い傾向があります。アスファルトは土よりも水の浸透が遅く、水はけが悪いため、都市部で内水氾濫が起きると水が引きにくくなってしまうのです。
高潮
高潮とは台風などによって平常時よりも海面が高くなることです。大気圧が1hPa低下すると海面は約1cm上昇するため、台風の中心気圧が910hPa程度になると、海面が約1m上昇します。(※)
平常時よりも海面が高くなることで、陸地に海水が流れ込む可能性があります。洪水は河川が発生源になるのに対して、高潮の発生源は海です。高潮によって陸地に海水が流れ込んだ場合、その土地で塩害が起こることもあります。
※出典:2021年10月12日 高潮はどうして起こるの? | 国土交通省
津波
津波とは、海底で発生する地震に伴う海底地盤の隆起や沈降、海底の地すべりによって、周辺の海水が上下に変動することです。
東日本大震災による津波が記憶に新しい方も多いのではないでしょうか。津波は海面を伝って震源から遠く離れた地域へ押し寄せることがあり、東日本大震災による津波はハワイやアメリカ西海岸への到達が確認されています。
03企業ができる水害対策とは
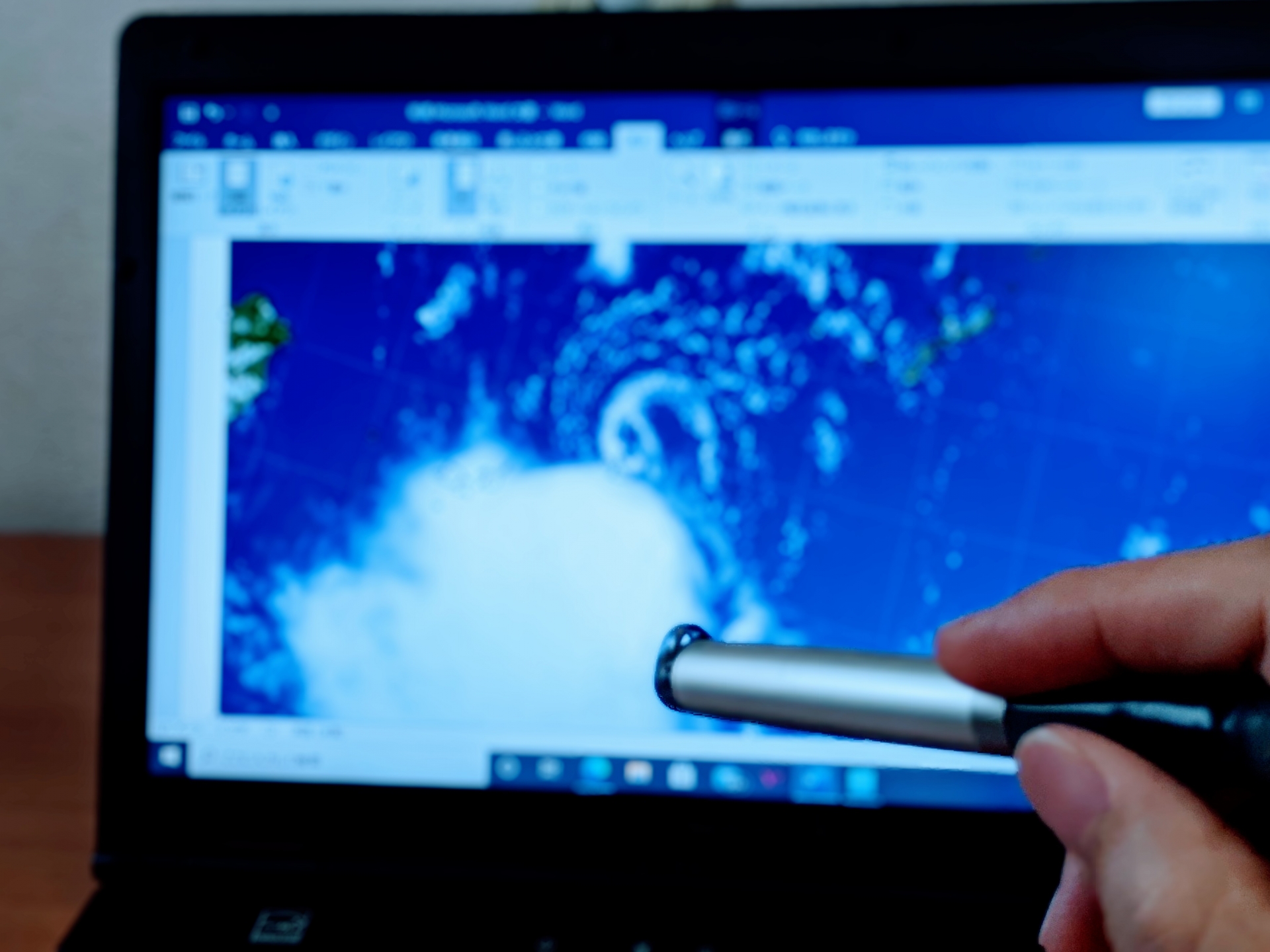
企業が水害に巻き込まれると通常業務ができなくなり、大きな損害が発生してしまうこともあります。企業と従業員の命を守るために、平常時から水害対策を行うことが大切です。ここでは、企業ができる水害対策についてご紹介します。
地域の水害危険度を把握する
水害対策を行う際は、地域の水害危険度を把握することから始まります。水害危険度は「リスクマップ(ハザードマップ)」から確認可能です。リスクマップとは、その地域で起こる災害の種類や規模を予測し、避難所の位置や安全な避難経路を書いた地図のことです。リスクマップは国土交通省がインターネット上に公開しているもののほか、各自治体が発行している紙のマップがあります。(※)
※出典:ハザードマップポータルサイト ~身のまわりの災害リスクを調べる~ | 国土交通省(2021年11月12日)
水害を想定したBCPを策定する
BCP(Business Continuity Plan)とは、事業継続計画を指し、自然災害やシステムエラーなどが発生した際であっても、直ちに事業の復旧・継続が行えるような計画を策定することです。
BCPでは従業員の安否情報確認など従来の防災計画に加え、「優先業務の特定」「優先業務の復旧時間の設定」「代替手段の業務継続方法」の3つを明確にする必要があります。BCPで具体的な行動まで策定することで、非常事態でもスムーズに対応できるでしょう。
浸水対策用品を設置する
水害から企業を守る方法として、浸水対策用品を設置することは効果的です。浸水対策用品として土のうや水のう、止水板などが挙げられます。
水は出入口から侵入してくると思われがちですが、トイレや水道の排水口から逆流してくることもあるため注意が必要です。水害の発生が予想される場合は、排水口に土のうや水のうを置いて塞ぎましょう。
災害保険に加入する
ハザードマップを確認し、あらかじめ大きな被害が想定される場合は災害保険に加入するのも一つの手です。災害保険には水害による補償プランもあるため、想定被害に見合ったプランに加入することをおすすめします。万が一のことが起きたとしても、災害保険に入っておくことで事業復旧にかかるコストに充てることが可能です。
04水害対策を行って会社と従業員の安全を守ろう
今回は水害の種類や企業ができる水害対策についてご紹介しました。「災害は自分とは無縁」と思っていても、災害大国である日本にいる以上、いつどのような災害が起きてもおかしくありません。
企業は営業利益を追い求める以前に働く従業員の命を災害から守る必要があります。今回ご紹介したような対策を事前に行い、水害に備えましょう。
監修者情報:株式会社パスカル
オクレンジャー ヘルプデスク
オクレンジャーヘルプデスクは、年間6000件以上のお客様の声と向き合い、課題を解決してきたオクレンジャーを知り尽くす専門部隊です。
業界随一のサポート体制を目指し、日々お客様の声や社会情勢、最新の防災情報等を勉強し情報収集することで、お役に立てるよう邁進しています。





