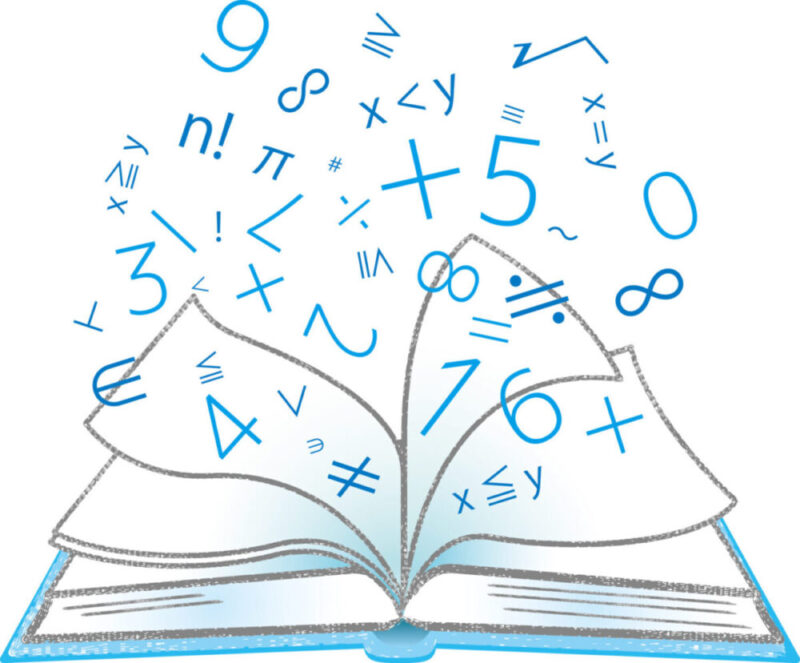日本を襲った過去の大規模地震を振り返る~大地震による被害と教訓~

日本は、地震や火山活動が活発な環太平洋変動帯に位置しており、世界面積のわずか0.25%という小さな国土面積に対して、地震発生回数の割合は全世界の18.5%と非常に高いのです。
地震大国と呼ばれる日本では、一人一人が地震の恐怖に対する知識と備えを持つことが重要です。過去の大地震とその影響、被害を振り返り、いつ起こるか分からない地震への日頃の備えを見直してみてください。
目次
01兵庫県南部地震(呼称:阪神・淡路大震災)の被害と教訓 02新潟県中越地震の被害 03東北地方太平洋沖地震(呼称:東日本大震災)の被害と教訓 04熊本地震の被害と教訓 05北海道胆振東部地震の被害と教訓 06福島県沖地震の被害と教訓 07能登半島地震の被害と教訓 08まとめ01兵庫県南部地震(呼称:阪神・淡路大震災)の被害と教訓
1995年1月17日5時46分、兵庫県南部を震源として発生した直下型地震であり、神戸と洲本で震度6を観測したほか、東北地方から九州地方にかけて広い範囲で震度5~1を観測しました。

通信途絶
各家庭と電話局を結ぶ加入回線(電話線)に大きな被害があったほか、停電で交換機が稼働できず電話回線が使用不能となり、兵庫県南部地域の全回線の約2割にあたる28万5千回線が被災しました。
火災による被害拡大
地震直後に地震動の大きかった地域を中心に火災が多発。その後1時間以上経過しても断続的に火災が発生しました。地震の数時間後およびその翌日以降の火災は、避難中の留守宅などで送電回復に伴う火災が初期消火されずに発生したとされています。
この地震による教訓
-
予防対策
死者の8割が家屋の倒壊や家具の転倒による圧迫死であったため、建築物の耐震基準や家具の固定が重要視されました。また、1980年以前に建設されたコンクリート橋脚が崩壊したことで、耐震設計以前の基準で建設されたコンクリート橋脚はじん性に乏しかったことが分かりました。耐震改修法の制定、耐震診断・改修促進のための支援措置が設けられました。
-
応急対策
大震災直後には被害情報が収集できず、被害規模の把握が困難でした。そのため、被害規模を即時的に推計し、それを初動対応にも活用できるような被害の早期評価システムが整備されました。また、初期情報の収集・連絡体制を充実するため、内閣情報集約センター、緊急参集チームが設立されました。
道路の損壊や車両の集中による渋滞に加え、鉄道、港湾の損壊も著しく、要員、物資等の緊急輸送に支障が生じ、食料や物資の輸送を著しく困難にしました。そこで、緊急輸送ルートの確保の重要性が再認識されました。
患者搬送にあたっては、最も威力を発揮するヘリコプターの活用が本格化したのは4日目以降でした。ヘリコプター活用が低調だった理由として、平常時における医療機関等の活用経験がほとんどなく関心が低かったことが挙げられます。このことから、発災直後から重篤患者を被災地外へ円滑に搬出するための活動計画を定めた医療搬送アクションプランを策定しました。
-
災害に強いまちづくり
直下の大規模地震にも耐えうるよう、各種施設等の耐震基準の見直しが進められました。また、避難場所や避難経路の整備、小・中学校の耐震化など、地震に強いまちづくりを総合的かつ計画的に実施するため、地震防災対策特別措置法が制定されました。
02新潟県中越地震の被害
2004年10月23日17時56分、新潟県中越地方を震源とした直下型地震であり、震度計による観測が始まって以来初めてとなる最大震度7を観測しました。
交通網寸断で集落が孤立
直近発生した台風により、地盤が緩んでいたことで土砂災害の被害が拡大しました。集落が孤立したほか、住民の避難を困難にし、その後の救援物資の搬入やライフライン復旧の大きな障害となりました。
被災後のストレス
本震後2か月間で計877回の余震を記録しており、怯え続け孤独死される高齢者の方がいたほか、いつ倒壊するか分からない家屋への入居を恐れ、車内で寝泊まりするなどの肺塞栓症(エコノミー症候群)で亡くなる方もいました。
03東北地方太平洋沖地震(呼称:東日本大震災)の被害と教訓
2011年3月11日14時46分、三陸沖を震源とする戦後最大の超巨大地震であり、宮城県で震度7、その近県4県で震度6強を観測したほか、北海道から九州にかけて広い範囲で揺れを観測しました。

大津波による被害
震源地に近い三陸海岸では多くの地域で浸水高が20~30mを超過する大津波を観測したほか、全国の沿岸で津波を観測しました。特に高い津波が到来した宮城県、岩手県、福島県では人的被害の99%を超える19,214名の被災者が出ました。
原子力発電所による影響
太平洋沿岸部に立地する東京電力福島第一原子力発電所の原子炉を緊急自動停止させる事態となりましたが、大津波により全電源が喪失し、原子炉の炉心冷却機能が停止しました。その後、水素爆発と火災が確認されたほか、放射性物質が外部へと放出される事態へ発展し、半径20km圏内が「警戒区域」として立ち入り禁止となりました。
液状化現象
埋立地として認識されていた地域のみならず、利根川沿いをはじめ、埼玉県や千葉県等の内陸部でも液状化により住宅が傾くなどの被害が多数発生しました。
この地震による教訓
-
災害対策とは、被害が大きかった現象に限らず、それ以外に起きた現象から得られる教訓等にも着目する必要がある。
-
災害対策の検討は、楽観的な想定ではなく悲観的な想定を行う必要がある。
-
被害を最小に留める「減災」のためには、地域、市民、企業といった多様な主体による様々な対策を組み合わせる必要がある。
-
発災直後は、十分な情報を得た対策はできない。不十分な情報の下でも災害対策を行えるよう、日頃の備えや訓練が必要である。
-
住民の避難や被災地方公共団体への支援は,甚大な被害が広範囲にわたって発生することを想定した上で、広域的な対応を行える制度にする必要がある。
-
得られた教訓は、防災教育等を通じて後世へしっかりと引き継いでいく努力を様々な場面で行う必要がある。
04熊本地震の被害と教訓
2016年4月14日21時26分、熊本県熊本地方を震源とする巨大地震であり、まず前震が発生、その後に本震が発生し、いずれも最大震度7を観測しました。
建造物の倒壊
構造部材や非構造部材等の部分的な損傷により、庁舎・体育館などの避難所や、病院・共同住宅等で、地震後に継続使用ができない事例が確認されました。
この地震による教訓
-
発災直後のパトロール車や避難車などの道路通行可否の情報収集
-
人命救助に伴う、道路構造物の応急復旧、応急復旧活動の支援
-
救援物資の輸送のための特許車両通行許可手続きや、関係者間の連携による渋滞対策
-
生活再建、復興支援のための道路交通可否情報の収集(再掲)、観光事業者への情報提供
-
将来への備えとして、ネットワーク機能の確保
05北海道胆振東部地震の被害と教訓
2018年9月6日3時7分、胆振地方中東部を震源として発生した地震であり、震度7を観測したほか、その翌年2月にかけて震度5弱~6弱程度の地震が度々発生しました。
土砂災害による被害
厚真町で山腹から大規模に土砂が崩れたことにより、民家を直撃したことで多数の死者と重軽傷者が発生しました。土砂災害は227件にも及ぶ被害をもたらしました。
断水、通信網の遮断
道内の68,249戸で約4日間の断水が発生しました。また、土砂災害の被害のあった地域では、10月上旬まで1カ月ほどの断水が続きました。また、地震による停電の影響で、各放送局にも影響がおよび、回線断絶や送電設備の故障などで情報を得られない事態も発生しました。
この地震による教訓
北海道胆振東部地震の震央から南東に80km離れた領域では、1982年に負傷者167人の被害をもたらした大地震が発生しています。過去の地震との海溝、プレートの沈み込みの関連性があり、やや深い場所で比較的規模の大きな地震の活発な地域になっていると考えられています。
気象庁は、大地震後の地震活動に対する防災上の呼びかけを実施することとしています。
-
大地震発生から一週間程度は、最初の大地震と同程度の地震への注意を呼びかけることを基本とし、過去の事例や地域特性に基づいた見通しや地震発生状況を発表する。
-
一週間程度以降は、余震発生確率の評価手法に基づいた最大震度◇以上となる地震の発生確率を、「当初の1/○程度」「平常時の約△倍」等の数値的見通しとして付加して発表する。
-
周辺に活断層等がある場合、地震調査委員会の長期評価結果等に基づいた留意事項を呼びかける。
-
防災上の呼びかけにおいては「余震」ではなく「地震」という言葉を用いる。
引用元:気象庁「災害時地震報告」
06福島県沖地震の被害と教訓
2021年2月13日23時7分に発生した福島県沖地震は、東日本大震災の余震とみられており、最大震度は震度6強(宮城県や福島県)であり、関東地方でも強い揺れを観測しました。
ライフラインの寸断
停電は約85万戸に及び、最大で翌日まで電力が復旧しなかった地域も多く、夜間の生活に支障をきたしました。停電による暖房や給湯設備の停止は冬季であったことから住民の健康への影響も懸念されました。
また、断水の影響で水道利用が不可能になり、一部地域では給水車による支援が必要となりました。飲料水の確保が困難だった住民も多く、災害時の備えとして水の備蓄が重要であることが再確認されました。
通信インフラについても一部で電話や携帯回線が通じにくい状況が報告されており、緊急時の情報伝達の重要性が改めて浮き彫りとなりました。
交通に関しては、東北新幹線が一部区間で数日間運休となったことで、地域間輸送に支障をきたしました。さらに、高速道路でも一部区間が地震による破損で通行止めとなり、物流の遅延に影響がでました。
経済活動への影響
経済活動についても被害の影響がありました。特に福島県沿岸部で地震の影響が出ており、一部の工場で生産ラインが停止し、復旧までに時間を要するなどの被害がでました。ただし、津波の発生はなく、東日本大震災のような甚大な被害には至らなかったことは幸いでした。
大型の地滑りはなかったものの、地盤が軟弱な地域では、一部で液状化現象が報告されています。この地震のインパクトは、生活基盤の停止や地域経済の一時的な停滞を含め、広範囲かつ多面的に影響を及ぼしたことです。
この地震による教訓
最も重要なのは、余震が長期間にわたり発生しうることを前提にした防災対策の必要性です。東日本大震災から10年が経過し、「災害が落ち着き、日常が戻った」と考えていた人も多かった中での地震発生は、余震の可能性を長期的に考慮し続けるべきであることを再認識させました。余震の発生に備えるには、防災設備やインフラを再度点検・補強することが不可欠です。
07能登半島地震の被害と教訓
2024年1月1日16時10分に石川県能登地方を震源として発生した最大震度7の地震であり、発生後1か月以内で震度5強以上の地震が頻発しました。
地理的条件による被害
震度7を記録した輪島市を中心に多くの建物が倒壊・焼失し、住宅や公共施設の損壊が目立ちました。
また、半島の地理的条件が重なり、道路や水道、電気といったインフラが寸断され、特にアクセスが悪い集落では交通網の脆弱性から孤立化のリスクが顕著となり、深刻な被害をもたらしました。
避難生活の困難と二次的被害
寒冷な冬季の発災という条件は避難環境を厳しいものにしました。トイレ不足、段ボールベッドの導入やプライバシーの確保が不十分な避難所では、避難者が感染症や低体温症といった二次的被害に直面しました。地震による直接死者に加え、避難生活中のストレス、持病の悪化、感染症などが原因で災害関連死も確認されています。
過疎地域の対応
過疎化や高齢化が進む地域では、孤立化した集落への支援の遅れもあり、復旧活動や被害対応が難航しました。これにより、地域全体の復旧・復興が遅れるなどの影響が出ました。
この地震による教訓
「自助」と「地域に根ざした防災対策」の重要性です。
災害時、公助(行政や団体からの支援)は即座に届かない場合が多く、住民個々の備えが命を守るための鍵となることが再認識されました。地震発生後の避難環境の悪化や二次災害の発生は、「防災意識の維持」と「個人での防災準備」の必要性を強調する結果となりました。また、地域特有の課題への対応として、過疎化、高齢化を考慮したきめ細やかな防災計画の推進が求められます。
さらに、情報共有やデジタル技術の活用の必要性も浮き彫りになりました。災害時に混乱を回避して、支援活動を効率化するためには、ICTを活用した迅速で正確な情報共有体制の整備が不可欠です。
08まとめ
これまでの地震を振り返ると、通信網途絶や交通網寸断、断水などライフライン被害はどうしても避けられない事態です。様々な分野で専門家、企業が「これまでの教訓」を活かしていますが、それだけでは減災になりません。
いつ起こるか分からない地震への備えは、政府だけでなく私たち一人一人が意識したいものです。身の回りにどのような危険が及ぶのかを考え、いざという時の避難場所、安否確認ツール、防災対策など被害を可能な限り少なくするために必要な対策を講じることが重要です。
※本記事は、下記参考HPを基に株式会社パスカルが作成しました。
※災害写真は(財)消防科学総合センター様よりお借りしています。
監修者情報:株式会社パスカル
オクレンジャー ヘルプデスク
オクレンジャーヘルプデスクは、年間6000件以上のお客様の声と向き合い、課題を解決してきたオクレンジャーを知り尽くす専門部隊です。
業界随一のサポート体制を目指し、日々お客様の声や社会情勢、最新の防災情報等を勉強し情報収集することで、お役に立てるよう邁進しています。